
司法書士の試験では、午前と午後の「択一式」において基準点を獲得した人だけが「記述式」の採点対象となりますが、択一式の基準点を獲得した場合でも、記述式での基準点をとることができなければ合格できません。
択一式での基準点獲得が第一のハードルだとすれば、第二のハードルとなるのが記述式。
今回は、この司法書士試験の鬼門とも言える記述式の対策についてご紹介いたします。
記述式の基準点や、よくあるミス、そして合格者がやっている記述対策のコツを紹介しますので、チェックしておきましょう。
記述式の基準点
司法書士試験の記述式は、2024年度より配点が倍になり、以前の70点満点から140点満点へと変わり、記述式の基準点は83点でした。
第一のハードルを越えた午前と午後の択一式の基準点到達者のうち、約30%の方が記述式の基準点をクリアし合格を獲得しています。
出題の難易度は例年から大きな変化は見られませんでしたが、配点が倍になったことで、時間内に解答用紙に正確な解答をどれだけ記載できたかが問われるようになりました。
よくあるミス
司法書士試験の記述式では、過去に出題された問題は出題されません。そのため、過去問を解いても意味がないと感じて過去問を行なわないという方もいるようです。
しかし、過去問を解くことで、司法書士試験の出題傾向や独特の雰囲気を感じることができ、また、同じ論点が繰り返し出題される傾向もあるため、過去問への取り組みは重要だと認識しておきましょう。
また、択一式の基準点をクリアしたものの記述式で落ちてしまった方の中には、翌年の試験対策を記述式への対策に絞って行う方もいるようです。しかしその結果、択一式で基準点をクリアできなかったというミスも見られます。
記述対策のコツ
合格者が行っている記述対策のコツは、本番を想定した練習を繰り返し、時間配分の感覚を身に付けることです。
そのためには、まずは「ひな形集」を活用して繰り返し書いて、スピーディーに書けるようにしておくことが大切です。
記述式問題集では、読んで理解するだけではなく、実際に手を動かして書く練習も重要です。読めても書けないという漢字が出てきたり、文字数に合わせてまとめるということも繰り返し行っておくことをおすすめします。
記述対策には、インプットだけでなく繰り返しのアウトプットの練習が大切だということを理解しておきましょう。
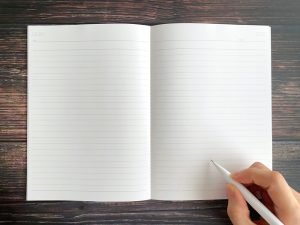
司法書士試験の記述式の基準点や、よくあるミス、そして合格者がやっている記述対策のコツをご紹介いたしました。
択一式の基準点を超えることができたら、合格が見えてきます。記述式への対策にも力を入れて合格を勝ち取りましょう。
コラムの運営会社

株式会社東京法経学院は10年以上にわたり、土地家屋調査士・測量士補・司法書士・行政書士など、法律系国家資格取得の受験指導を行ってきました。
通学・通信講座の提供だけではなく、受験対策用書籍の企画や販売、企業・団体の社員研修もサービス提供しています。
詳細は、各サービスページをご確認ください。
土地家屋調査士試験、測量士・測量士補試験、司法書士試験、行政書士試験、公務員試験



